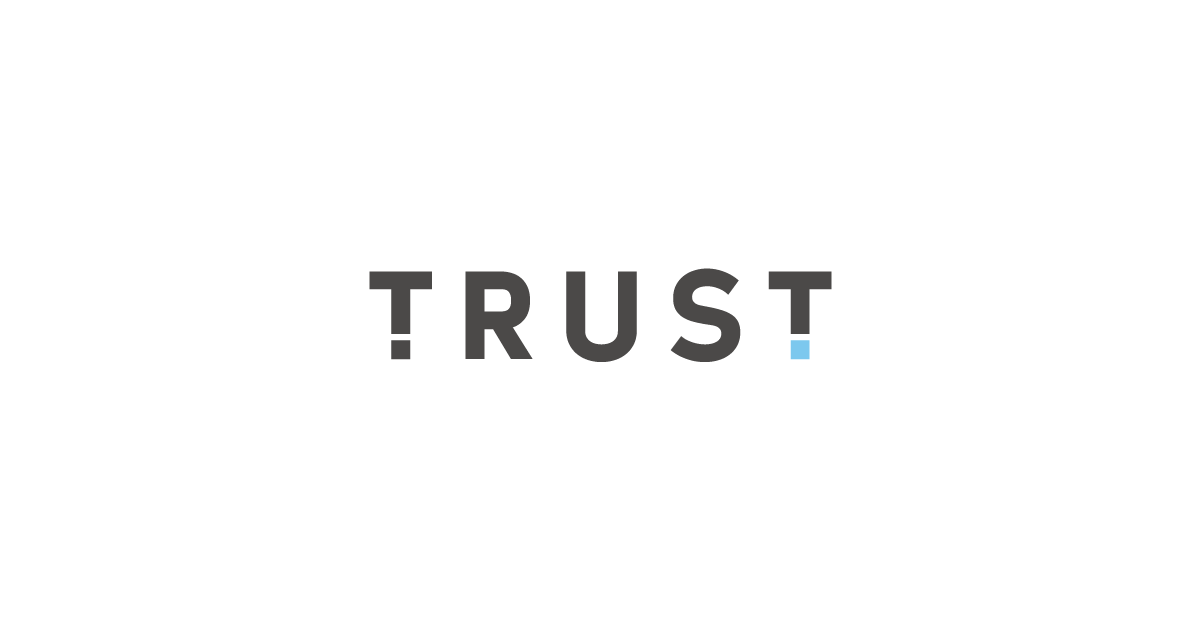2025.03.17 2025.02.06オフィス経営
オフィスにおけるBCP対策!オフィスビルの選び方や環境整備・参考事例などを紹介

本記事で、オフィスにおけるBCP対策(オフィスビルの選び方や環境整備)を解説します。またBCP対策を進めたオフィスの参考事例もご紹介します。オフィスの開設や移転、リニューアルなどをご検討中の方は、ぜひご覧ください。
オフィスにおけるBCP対策の基本情報

オフィスにおけるBCP対策を検討する前に、基本情報を確認しましょう。基本情報を確認することで、BCP対策を検討しやすくなるからです。それではBCP対策の定義と目的、メリット、デメリット、手順をご紹介します。
BCPとは?(定義と目的)
まずBCPとは「Business Continuity Plan」の略称で、「事業継続計画」と訳されます。主な目的は、緊急事態における企業の事業継続や来訪者の保護、迅速な復旧などです。
中小企業庁によると、「企業が自然災害、大火災、テロ攻撃などの緊急事態に遭遇した場合において、事業資産の損害を最小限にとどめつつ、中核となる事業の継続あるいは早期復旧を可能とするために、平常時に行うべき活動や緊急時における事業継続のための方法、手段などを取り決めておく計画」とBCPが定義されています。
メリット
次にオフィスにおけるBCP対策のメリットは、緊急事態時の落ち着いた対応や社会的な信頼の獲得などです。日ごろからBCP対策を周知しておくことで、緊急事態時に落ち着いて対応しやすくなります。
また緊急事態時の対応を明確に示しておくことで、取引先や消費者から信頼をを得やすくなります。緊急事態が発生しても来訪者を保護し、迅速に復旧をしながら業務を継続できれば、取引上の悪影響を最小限に抑えられるからです。
デメリット
しかしBCPを策定するコストや実行するためのコストなどは、オフィスにおけるBCP対策のデメリットです。BCPを策定するためにコンサルティングを依頼したり、対策を周知するためのミーティングを開催したりするコストがかかります。
またBCPを実行するためには、サテライトオフィスを導入したり、緊急連絡用のシステムを導入したりするコストもかかります。データをバックアップするサーバーや貯水タンクなどの設備を設置する場合にも、コストが必要です。
手順
それからBCP対策を進める手順も確認しましょう。
- 方針を決定する
- 自社の事業内容を整理して体制を整備する
- 社内へ共有して社外へ周知する
- 定期的に評価・改善する
以上の手順を踏むためには数か月から半年以上がかかります。事業内容ごとにリスクを評価して、優先度の高い事業から対策を講じましょう。社会情勢や事業内容の変化に対応するためには、定期的にBCP対策を評価・改善することが重要です。
BCPを考慮したオフィスビルの選び方

基本情報を踏まえたうえで、BCPを考慮したオフィスビルの選び方も確認しましょう。オフィスビルがBCP対策に影響を与えるからです。それでは6点(周辺環境と耐震性、非常用電源、貯水タンク、備蓄倉庫、防犯性)に分けてご紹介します。
周辺環境
まず周辺環境が、BCPを考慮したオフィスビルの選び方です。ハザードマップを調査すると、オフィスビルの周辺環境の災害リスクを把握できます。ハザードマップには、災害リスクの高い場所や避難場所などが示されているからです。
地盤は、地震の揺れの強さに影響します。一般的には地盤が強固な土地は軟弱な土地に比べて揺れにくいため、同じ揺れによる被害が少なくなります。したがって災害リスクの高い場所や地盤の軟弱な土地にあるオフィスビルを避けましょう。
参照元:地震本部「地盤」
耐震性
次に耐震性も、BCPを考慮したオフィスビルの選び方です。オフィスビルの耐震性を確保するために、「新耐震基準」を満たしているオフィスビルを選びましょう。「新耐震基準」では、大規模地震(震度6強〜7程度)でも倒壊しない構造が求められているからです。
参照元:国土交通省「資料2住宅・建築物の耐震化に関する現状と課題 関係」(1-2ページ)
ただし旧耐震基準によって建てられたオフィスビルであっても、耐震改修工事によって新耐震基準を満たしている場合があります。オフィスの耐震診断や耐震改修工事についてまとめてありますので、次の記事も併せてご覧ください。
非常用電源(発電機・蓄電池)
続いて非常用電源(発電機・蓄電池)も、BCPを考慮したオフィスビルの選び方です。緊急事態時に電気が止まってしまっても、発電機で自家発電ができます。また自家発電した電気を蓄電池に貯めておけば、数時間~数日にかけて電力の確保が可能です。
非常用電源が設置されていないオフィスビルであっても、発電機や蓄電池を設置できる場合がありますので、オフィスビルのオーナーに相談しましょう。オフィスの電気工事についてまとめてありますので、次の記事も併せてご覧ください。
貯水タンク
それから貯水タンクも、BCPを考慮したオフィスビルの選び方です。貯水タンクに必要な量の水を蓄えておけば、非常事態時の断水に備えられます。ただし地震や台風などに耐えられる強度が必要です。
オフィスビルに強度の高い貯水タンクが設置されている場合でも、保守点検やメンテナンスが必要です。非常事態時に安全な水を供給するためには、貯水タンクに定期的な清掃や消毒が求められます。
備蓄倉庫
さらに備蓄倉庫も、BCPを考慮したオフィスビルの選び方です。緊急事態時に備えるために、備蓄倉庫に防災用品(簡易トイレやブランケットなど)や食料(水や長期保存できる食品など)などを保管しましょう。
東京都には「東京都帰宅困難者対策条例」が定められており、緊急事態時に従業員がオフィス内に留まれるように、事業者には3日分の水や食料の備蓄が求められています。
防犯性
そして防犯性も、BCPを考慮したオフィスビルの選び方です。オフィスに対する犯罪行為(強盗やテロ、サイバー攻撃など)を未然に防いだり、発生時には被害を最小限に抑えたりするために、防犯性の高いオフィスビルを選びましょう。
例えば防犯カメラや入退館(室)管理システム、インターネットセキュリティツールなどが、オフィスのセキュリティ対策に役立ちます。オフィスセキュリティ対策に役立つツールやシステムを詳しくまとめてありますので、次の記事も併せてご覧ください。
BCPに基づくオフィス環境整備のポイント

BCPを考慮してオフィスビルを選んだら、環境整備が必要です。それではBCPに基づくオフィス環境整備のポイント(設備・機器・什器の転倒防止と防災訓練、避難経路の確保、緊急連絡・安否確認の方法、データのバックアップ体制、オフィスの分散化)をご紹介します。
設備・機器・什器の転倒防止
まず設備・機器・什器の転倒防止が、BCPに基づくオフィス環境整備のポイントとして挙げられます。地震の揺れで設備・機器・什器が転倒すると、従業員が怪我をしたり、オフィス環境に支障が出たりする恐れがあるからです。
例えば背の高い設備・機器・什器を配置する場合には、床や壁に直接固定したり、突っ張り棒・転倒防止ジェルを活用したりします。オフィスメンテナンスの重点箇所と方法をまとめてありますので、次の記事も併せてご覧ください。
防災訓練
次に防災訓練も、BCPに基づくオフィス環境整備のポイントです。定期的な防災訓練の実施は従業員の防災意識を向上させながら、緊急事態時の正しい行動を定着させます。BCP対策の理解を深めるためにも必要です。
定期的に防災訓練をすることで、緊急事態時の行動に関する改善点を考えやすくなります。防災訓練の評価・改善を繰り返しながら、BCPをアップデートしましょう。オフィスの防災マニュアルをまとめてありますので、次の記事も併せてご覧ください。
避難経路の確保
続いて避難経路の確保も、BCPに基づくオフィス環境整備のポイントです。緊急事態時に従業員や来訪者が迅速に避難できるように、安全な避難経路を定めましょう。安全な避難を促すためには、避難経路マップを掲示して周知しておくことが重要です。
なお避難経路の確保は消防法によって定められていますので、法令を遵守しなければなりません。オフィスのレイアウトに対する消防法の規定をまとめてありますので、次の記事も併せてご覧ください。
緊急連絡・安否確認の方法
それから緊急連絡・安否確認の方法も、BCPに基づくオフィス環境整備のポイントです。緊急事態時に迅速に対応できるように、緊急連絡・安否確認の方法をマニュアルにまとめて従業員に周知しましょう。
個別の電話・メール・SNSの利用はコミュニケーションの効率性が低く、緊急事態時に機能しない恐れがあります。緊急事態時に対応できる安否確認ツールの導入や災害に強い通信環境の整備が必要です。
データのバックアップ体制
さらにデータのバックアップ体制も、BCPに基づくオフィス環境整備のポイントです。距離の離れた拠点やクラウドサーバーなどに、事業継続に必要なデータ(顧客情報や契約書、製品情報など)をバックアップしておきましょう。
一か所にデータをまとめて保存していると、緊急事態時にサーバーが故障・破損した場合に全てのデータを失ってしまう恐れがあります。データのバックアップ体制を整備したうえで、データを失ってしまった際の復旧方法も確保しておきましょう。
オフィスの分散化(テレワーク・サテライトオフィスなど)
そしてオフィスの分散化(テレワーク・サテライトオフィスなど)も、BCPに基づくオフィス環境整備のポイントです。オフィスの分散化によって、感染症や自然災害などに対応できます。
例えばテレワークは、人混みを避けて仕事ができるため感染対策に向いています。サテライトオフィス(本拠地から離れた場所に設置されるワーキングスペース)を開設しておけば、本社オフィスが被災しても事業を継続できます。
BCP対策を進めたオフィスの参考事例
ポイントを押さえて環境整備を進めるために、BCP対策を進めたオフィスの参考事例を調査しましょう。事例5点を取り上げて、各事例の特徴(安否確認システムとデータバックアップ、テレワーク、非常用発電設備、水害対策)を紹介します。
安否確認システムを導入した自動車製造販売会社

まず「宮城トヨタ自動車」は、安否確認システムを導入した自動車製造販売会社です。東日本大震災の際に従業員の安否確認に1週間かかった経験を教訓にして、BCP対策として安否確認システムが導入されました。
ネットワークの安定性や地震発生情報に連動したメール自動送信機能を重視して、導入する安否確認システムが検討されました。防災関連アンケートも実施され、従業員の防災意識向上に努めているBCPを進めたオフィスの参考事例です。
参照元:Yahoo!安否確認サービス「宮城トヨタ自動車様導入事例」
データのバックアップ体制を整備したコンピューターソフト会社

次に「株式会社エイビス」は、データのバックアップ体制を整備したコンピューターソフト会社です。BCP対策として本社と支社のデータが相互に保存されているため、緊急事態時に補完しあえます。
BCPの課題を検討する委員会が月1回開催され、従業員の提案を踏まえながら必要に応じてBCPの内容がアップデートされています。従業員の防災意識の向上につながるBCP対策を進めたオフィスの参考事例です。
参照元:
九州経済産業局「テーマ:経営資源の保護 – タイトル:本社と支店のデータを相互に バックアップ」
テレワークを導入した店舗内装工事会社

続いて「株式会社シンク・タンク」は、テレワークを導入した店舗内装工事会社です。BCP対策としてテレワークが導入されたことで、新型コロナウイルス感染拡大時にも事業継続が可能でした。
自然災害対策として、周辺のハザードマップを元にした避難経路や避難場所がオフィス内に掲示されています。避難経路を塞がないようにオフィス内の整理整頓を心がけているBCP対策を進めたオフィスの参考事例です。
参照元:中小企業基盤整備機構「株式会社シンク・タンク|BCPはじめの一歩 事業継続力強化計画をつくろう」
非常用発電設備を導入した物流会社

それから「沼尻産業株式会社」は、非常用発電設備を導入した物流会社です。電力供給が止まっても配送に必要な情報にアクセスできるように、BCP対策として非常用発電設備が導入されています。
またトラックの燃料を確実に調達できるように、自家用給油所も導入されています。災害発生から2日以内に事業を再開できるように、緊急連絡手段の衛星電話も設置しているBCP対策を進めたオフィスの参考事例です。
参照元:J-Net21「目標は2日以内の事業復旧「沼尻産業株式会社」 | 備えあれば憂いなし、BCPのススメ」
水害対策を取り入れた金属製品製造業者

そして「株式会社ヤスナガ」は、水害対策を取り入れた金属製品製造業者です。水害対策を取り入れたBCPが策定されており、浸水を避けるために備蓄品や復旧作業用具(デッキブラシや高圧洗浄機など)が高所に保管されています。
また従業員の安全を確保するために、気象・警報レベルに応じた出社体制が整備されています。緊急連絡網や出社時の車両乗り合い制度も整備しているBCP対策を進めたオフィスの参考事例です。
参照元:九州経済産業局「タイトル: 復旧作業に使用する掃除道具類を高い場所に配置」
オフィスのBCP対策を進めよう!
IDEALは、オフィスのコンセプト設計から資金調達、物件探し、内外観のデザイン・工事、集客までのワンストップソリューションをご提供しております。
下のキーワードをクリックして、オフィスデザインや内装工事などの関連記事もぜひご覧ください。またオフィスの開業や移転、リニューアルなどをご検討の際は、ぜひご相談ください。