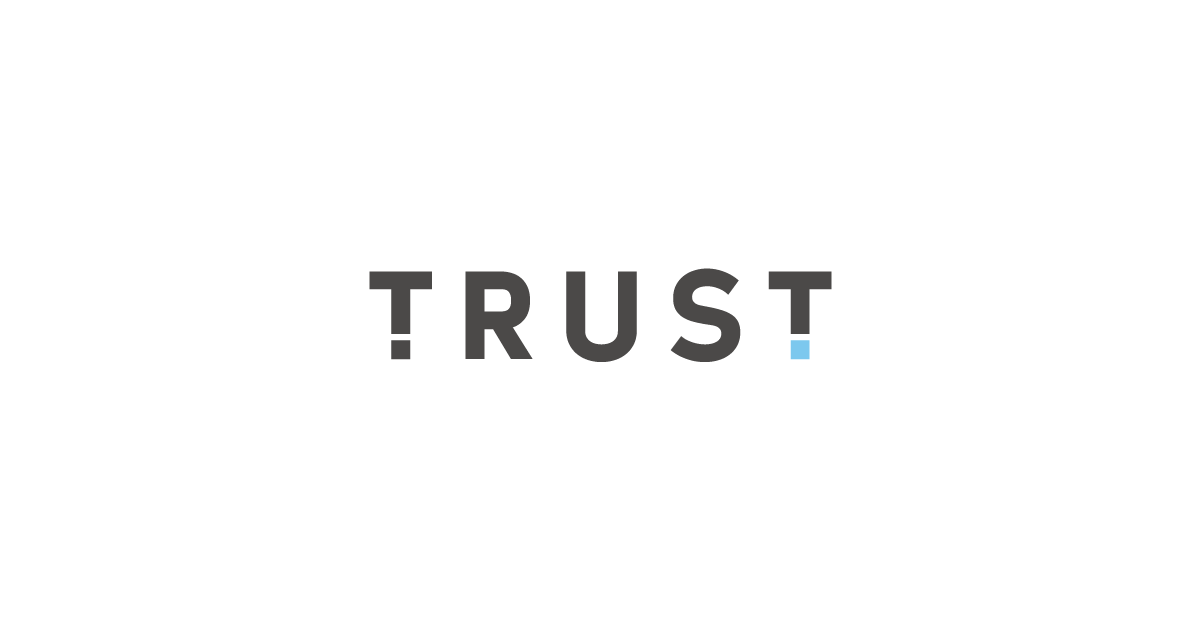2021.04.29 2023.12.11オフィス新設・開設
シェアオフィスとは?基本情報・開業する流れ・内装デザイン・施工事例を紹介

本記事では、「シェアオフィスとは?」という疑問にお答えするために、シェアオフィスの基本情報・開業する流れ・内装デザイン・施工事例をご紹介します。オフィスの開業や移転、リニューアルなどをご検討中の方は、ぜひご覧ください。
目次
シェアオフィスとは?基本情報を紹介

そもそもシェアオフィスとは、どういった職場環境でしょうか?そこでシェアオフィスの基本情報(定義と市場規模、利用者のニーズ、コワーキングスペースとの違い)をご紹介します。基本情報を押さえたうえで、シェアオフィスの導入を検討しましょう。
定義
まずシェアオフィスとは、「複数の企業や個人が共同で利用できるオフィス物件」です。一般的にはオフィスの機能性を確保するために、執務室や会議室、休憩室などがレイアウトされ、通信設備やOA機器なども導入されています。
シェアオフィスを利用するメリットは、一軒のオフィス物件を共同で利用することで、コスト(賃料や光熱費、設備・機器・什器費など)を抑えられる点です。ただしプライバシー保護やセキュリティ確保の難しさなどは、デメリットです。
市場規模
次にシェアオフィスの市場規模は、2010年代から拡大傾向です。シェアオフィスを含むフレキシブルオフィスの拠点数が、10年連続で増加。東京23区内だけではなく、より住環境に近い郊外エリアでの開設も増加しています。
シェアオフィスの市場規模が拡大している要因は、テレワークなどの多様な働き方の広がりやフリーランス人口の増加などです。低コストでオフィス環境を確保して、利用する時間や場所を自由に選びたい場合に、シェアオフィスが適しています。
参照元:ザイマックス総研の研究調査「フレキシブルオフィス市場調査2023」
利用者のニーズ
そしてシェアオフィスに対する利用者のニーズには、幅広い用途のスペースや設備・サービスなどがあります。例えば業務内容や従業員数などに応じて、執務室や個室、会議室、休憩室などが必要です。
また利用者のニーズに応えて、通信設備やOA機器、個人用ロッカー、郵便受け、宅配物の受け取りサービスや登記サービスなども提供されています。自宅でのリモートワークでは対応できない業務でも、シェアオフィスなら対応しやすいです。
コワーキングスペースとの共通点と相違点
シェアオフィスとコワーキングスペースとの共通点は、複数の企業や個人が共同利用する点です。どちらにおいても、幅広い用途の部屋(執務室や会議室、個室など)や設備・機器・什器などが提供されます。
一方で利用者同士の交流は、シェアオフィスとコワーキングスペースの相違点です。シェアオフィスは、主に自社内での作業や会議のために利用されますが、コワーキングスペースは、利用者同士の交流や外部向けのイベントなどにも利用されます。
シェアオフィス事業を開業する流れ

基本情報を押さえたうえで、シェアオフィス事業の開業する流れも確認しましょう。開業する流れを把握することで、スムーズに開業準備を進められるからです。それでは5点(事業計画と資金調達、物件選定、内装・外観、届出・許可)に整理して、ご紹介します。
事業計画の立案
まずシェアオフィス事業を開業する流れは、事業計画の立案から開始されます。事業計画書は、事業の戦略やコンセプトなどが記載される書類です。事業の評価・改善や融資・補助金の申請などに活用されます。
そこで市場調査を行い、シェアオフィスのコンセプトを設計したうえで、事業計画書にまとめましょう。シェアオフィスのターゲットやポジションを明確にすることで、必要なサービスやオフィスのデザインなどを決めやすくなります。
開業資金の調達
次にシェアオフィスの事業計画に基づいて、開業資金の調達を開始しましょう。一般的なオフィスの開設費用は、坪単価30万~60万円程度です。開設後には、運転資金(毎月の賃料や光熱水費、人件費など)もかかります。
なお経営者の自己資金だけで開業資金を調達できない場合には、開業資金の調達方法(出資や借入、融資、補助金や助成など)を検討しなければなりません。オフィス開設費用の内訳などをまとめてありますので、次の記事も併せてご覧ください。
物件の選定
そしてシェアオフィス事業の開業資金調達と並行して、物件の選定も進めましょう。立地は、顧客がシェアオフィスを選ぶ際の重要なポイントです。ターゲットとしている顧客層が利用しやすい立地を特定しなければなりません。
例えば同じビル内や近隣に賑やかな店舗が営業していると、静かな作業空間を提供しづらくなります。オフィス物件の探し方やポイントなどをまとめてありますので、次の記事も併せてご覧ください。
内装・外観のデザイン・工事
それからシェアオフィス事業を開業する物件を契約できたら、内装・外観のデザイン・工事を計画します。顧客満足度の向上にとって、内装デザインが重要です。オフィスの内装をデザインする方法についてまとめてありますので、次の記事も併せてご覧ください。
そして外観のデザインは、集客にとって重要です。ターゲットとする顧客層の目に止まりやすい外観をデザインしましょう。おしゃれな外観をデザインするコツをまとめてありますので、次の記事も併せてご覧ください。
届出・許可の申請
なお内装・外観の工事を進めながら、シェアオフィスを開業するために必要な届出・許可の申請も進めましょう。届出・許可ごとに、申請の条件や方法が異なります。
- 開業届または法人設立届
- 納税に関する手続き
- 社会保険と労働保険の加入手続き(従業員を雇用する場合)
- 消防法に基づく届出
- 飲食店の営業許可(飲食物を調理して提供する場合)
参照元:
日本年金機構「事業所が健康保険・厚生年金保険の適用を受けようとするとき」
なお消防法に基づく届出についてまとめてありますので、次の記事も併せてご覧ください。
シェアオフィスの内装・外観をデザインする際の注意点

開業する流れだけではなく、シェアオフィスの内装・外観をデザインする際の注意点もご紹介します。8点(コンセプトと動線・レイアウト、配色、清潔さ、防音対策、空調・換気設備、照明器具、メンテナンス性)を取り上げましたので、ご覧ください。
コンセプトの設計
まずコンセプトの設計が、シェアオフィスの内装・外観をデザインする際の注意点です。ターゲットとする顧客層のニーズとサービスの内容などを明確にしたうえで、オフィスデザインのコンセプトを設計しましょう。
例えば「個人作業も会議やイベントも可能なオフィス空間」をコンセプトにするなら、個室ブースや会議室をレイアウトして、防音対策も講じます。オフィスデザインのコンセプトを設計するコツをまとめてありますので、次の記事も併せてご覧ください。
動線設計とレイアウト
次に動線設計とレイアウトも、シェアオフィスの内装・外観をデザインする際の注意点です。顧客がスムーズに移動できて、使いやすさを感じる動線を設計したうえで、必要なスペース(個室や会議室、フリースペース、キッチンなど)をレイアウトしましょう。
例えばフリースペースと個室の間にトイレやキッチンなどの共有設備を設置すると、利用者同士の無駄な往来を減らせます。オフィスをレイアウトするポイントについてまとめてありますので、次の記事も併せてご覧ください。
配色
そして配色も、シェアオフィスの内装・外観をデザインする際の注意点です。配色を工夫することで、空間を広く見せたり、集中力を高めたりする効果が期待できます。また内装と外観の配色を調和させると、統一感のあるシェアオフィスをデザインできます。
例えばアースカラー(茶色や緑色など)をベースにした内装空間には、利用者の精神を落ちつかせる効果を期待できます。オフィスデザインにおける色の効果や適した色の種類などを紹介していますので、次の記事も併せてご覧ください。
清潔さ
また清潔さも、シェアオフィスの内装・外観をデザインする際の注意点です。内装・外観のデザインに清潔感がないと、集客と売上を伸ばしづらくなります。汚れが目立ちにくい配色や素材を選びましょう。
特にキッチンやトイレは汚れやすいので、注意が必要です。掃除のしやすい素材を選びましょう。オフィスのトイレをデザインするポイントを紹介していますので、次の記事も併せてご覧ください。
防音対策
それから防音対策も、シェアオフィスの内装・外観をデザインする際の注意点です。防音対策により、情報漏洩の防止や集中力の向上を期待できます。防音対策が不十分だと、利用者の満足度低下や不信感を招く恐れがあります。
例えば内装には防振性の高いカーペットを選択して、外観には遮音効果の高い外壁材を施工しましょう。オフィスの防音対策についてまとめてありますので、次の記事も併せてご覧ください。
空調・換気設備
さらに空調・換気設備も、シェアオフィスの内装をデザインする際の注意点です。空調設備は、業務効率やモチベーションをアップさせるために重要です。オフィスに空調設備をデザインする際のポイントを紹介していますので、次の記事も併せてご覧ください。
換気設備は、ウイルス・汚染物質の除去や二酸化炭素濃度の低下、結露とカビの防止などのために必要で、法的に設置しなくてはなりません。オフィスに換気設備をデザインするポイントを紹介していますので、次の記事も併せてご覧ください。
照明器具
続いて照明器具も、シェアオフィスの内装・外観をデザインする際の注意点です。オフィスデザインにおいて、照明器具には業務効率の向上やコンセプトの表現、省エネ化などの役割があります。
例えば業務効率を高めたいワークスペースには青白い昼光色の照明器具が合いますが、リラックススペースには温かみのある電球色が適しています。オフィスのおしゃれな照明デザインについて紹介していますので、次の記事も併せてご覧ください。
メンテナンス性
なおシェアオフィスの内装・外観をデザインする際の注意点には、メンテナンス性もあります。内装・外観のメンテナンス性が高いと、修繕や点検にかかるコストが少なくて済みます。
例えば内壁にビニールクロスを施工すると、手入れが簡単です。外壁に耐候性の高い塗料を塗ると、メンテナンス性を高められます。オフィスメンテナンスの重点箇所と方法をまとめてありますので、次の記事も併せてご覧ください。
シェアオフィスの内装施工事例
理想的なシェアオフィスの内装をデザインできるように、参考となる内装施工事例を調査しましょう。本記事では事例5点を取り上げて、内装デザインに関する魅力などをご紹介します。
白を基調とした内装デザイン

「WAW 日本橋」様は、日本橋駅前にあるシェアオフィスです。白を基調とした内装デザインで、開放感や清潔感があります。アクセントカラーは木材の茶色や植物の緑色で、温かみや癒しを感じさせるアースカラーです。
執務スペースには、業務に集中しやすいように派手な装飾や色味はなく、昼光色のシーリングライトが施工されています。個人用スペースは、パーテーションで区切られ、ダウンライトが施工されているため、作業に集中しやすい空間です。
参照元:WORK AND WONDER【WAW】「WAW 日本橋 」
シックな雰囲気の内装デザイン

「ビジネスエアポート 新橋」様は、新橋駅前にあるシェアオフィスです。全体的に落ち着いた色味の設備・機器・什器が設置されており、シックな雰囲気の内装デザインです。ただし天井と壁の色は白に統一されており、暗い雰囲気にならないように配慮されています。
また足音が気にならないように、執務室や会議室の床にはカーペットが施工。そして部屋の用途に合わせて、照明の色味や種類が異なります(ラウンジにはオレンジ色のペンダントライトなど、ワークスペースには昼光色のダウンライトなど)。
参照元:Business Airport「ビジネスエアポート 新橋」
ナチュラルテイストの内装デザイン

「H¹T阿佐ヶ谷」様は、阿佐ヶ谷駅にあるシェアオフィスです。茶色(壁材やカウンター)と緑色(椅子・植物)が取り入れられて、ナチュラルテイストの内装がデザインされています。アクセントカラーは、グレーやブラックです。
執務スペースの座席上部には、照明器具が設置されており、作業する際に手元が暗くならないように配慮されています。なお会議室の内装には白が多く配色されているため、明るい雰囲気を感じさせます。
参照元:H¹T阿佐ヶ谷「シェアオフィス」
防音対策された内装デザイン

「bizcube」様は、銀座駅にあるシェアオフィスです。個室の壁と天井に防音シートとグラスウールが施工されており、防音対策された内装デザインです。隣の部屋の音が聞こえないように、防音層が2重です。
また什器の色味(ダークブラウンのデスクとブラックの椅子)が揃っているため、空間全体に統一感があります。壁や床にはグレーが配色されており、シックな内装デザインです。
完全個室のレイアウトされた内装デザイン

「BIZ SMART 青山」様は、表参道駅にある24時間営業のシェアオフィスです。完全個室のオフィスがレイアウトされた内装デザインです。感染症対策として、個室ごとに個別の空調が完備されています。
さらに週5回のゴミ回収と週2回のルームクリーニングのサービスも付帯されています。清掃の手間をかけずに、オフィスの清潔さを維持できます。
参照元:ビズスマート「港区・青山のレンタルオフィスならBIZSMART青山」
シェアオフィスの導入や開業を検討しよう!
IDEALは、オフィスのコンセプト設計から資金調達、物件探し、内外観のデザイン・工事、集客までのワンストップソリューションをご提供しております。
下のキーワードをクリックして、オフィスデザインや内装工事などの関連記事もぜひご覧ください。また店舗の開業や移転、リニューアルなどをご検討の際は、ぜひご相談ください。